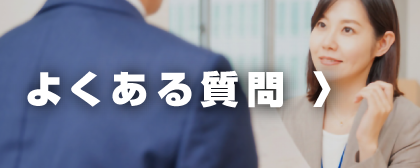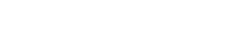用語集(基板実装関連)
基板実装(PCB Assembly)とは
電子機器の“心臓部”であるプリント基板に、抵抗・コンデンサ・半導体などの電子部品を「はんだ付け」技術で取り付ける工程を指します。スマートフォン、パソコン、自動車、産業機器などあらゆる製品が、基板実装によってその機能を実現しています。この工程では、温度制御・静電気対策・品質管理が極めて重要であり、精密な設備と技能が求められます。
はんだ付けの基本
はんだ付けの基本
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
アルコール洗浄(Alcohol Cleaning / IPA洗浄)
はんだ付け後のフラックス残渣や汚れを除去するための洗浄工程です。
一般的にはIPA(イソプロピルアルコール)を使用し、基板表面の清浄度を高め、腐食や絶縁不良の防止に役立ちます。
追いはんだ(Re-solder / 追いはんだ)
一度固まったはんだを再加熱し、はんだ量の調整や形状の修正を行う作業です。
はんだ不足や外観不良の改善、導通安定性の向上など、仕上げ・補修目的で用いられます。
仮止め(Tack Soldering / 仮付け)
部品を正しい位置に固定するために、軽くはんだ付けを行う作業です。
本格的なはんだ付け(本付け)の前に位置決め目的で行われます。
手はんだ(Hand Soldering / 手作業はんだ付け)
熟練作業者がはんだごてを使用して行う手作業でのはんだ付けです。
試作や精密部品、微調整、修理対応など、細かな品質対応に適しています。
ディップはんだ(Dip Soldering / ディップ槽はんだ付け)
基板や電子部品を溶融したはんだ槽に浸し、一括ではんだ付けを行う方法です。
大量処理や同一仕様の量産に適した実装方式ですが、熱ストレス管理や品質管理が重要となります。
また、適用条件として、リード部品が片面実装であり、はんだ槽に浸漬する面に表面実装部品(SMD)が搭載されていないことが必要です。
熱回復力(Heat Recovery / 熱回復性能)
加熱により温度が低下したはんだこて先が、設定温度まで素早く回復する性能のことを指します。
熱回復力が高いこては、連続作業でも温度が安定し、はんだ不良の発生を抑え、作業品質の向上に繋がります。
はんだ付け時間(Soldering Time)
はんだ付け時に加熱する時間のことで、適切に管理することで過熱による部品劣化や、加熱不足による未溶融・接合不良を防止できます。
適正なはんだ付け時間の管理は、品質安定と不良率低減に重要です。
はんだ付け温度(Soldering Temperature)
はんだ付けに使用する温度のことで、適正温度を管理することで部品破損や未溶融による接合不良を防止します。
温度が高すぎると部品や基板を損傷し、低すぎると濡れ不良・未溶融が発生するため、温度管理は品質確保の重要ポイントです。
引きはんだ(Drag Soldering / ドラッグはんだ)
多ピンICや細ピッチ部品の端子を、はんだごてを滑らせるように動かし、一度の操作でまとめてはんだ付けする技法です。
短時間で美しく仕上げることができ、ブリッジ(ショート)を防ぎながら効率良く実装できるのが特長です。
精度が求められるため、熟練したはんだ付け技術を必要とします。
フラックス(Flux / はんだ用フラックス)
はんだ付け時に金属表面の酸化膜を除去し、濡れ性(はんだの広がり)を向上させるための薬剤です。
はんだの流動性と接合品質を高め、不良発生の抑制に重要な役割を持ちます。
予備はんだ(Pre-tin / 予備はんだ付け)
部品の端子や基板のランドに、あらかじめ薄くはんだを付けておく工程です。
後工程でのはんだ濡れ性が向上し、接合品質が安定します。
リフロー(Reflow Soldering / リフローはんだ付け)
はんだペーストを塗布した基板に電子部品を配置し、加熱して一括ではんだ付けを行う工程です。
表面実装(SMT)で用いられる、電子機器製造の主要な量産プロセスです。
基板実装関連用語
6
V(ぶいかっと)カット(V-cutting / V溝加工)
基板を分割しやすくするために、基板の境界部にV字型の溝(スリット)を形成する加工技法です。
実装後の基板分割(面付け基板の切り離し)を容易にし、作業効率の向上に役立ちます。
ルーター加工(Router Cutting / ルーター分割)
基板の外形や分割ラインを、回転刃(ルーター)を用いて切削する加工方法です。
摩擦切削により基板を切り離すため、Vカットやミシン目よりも切断面が滑らかで、部品へのストレスが少ないのが特徴です。
主に、精密基板・割れや反りが心配な基板・実装密度の高い基板の分割に適しています。
認識マーク(Fiducial Mark / フィデューシャルマーク)
マウンタ(実装機)が基板上の位置を正確に認識するために配置される基準マーク(目印)です。
このマークをカメラで読み取ることで、部品搭載位置の座標補正が行われ、高精度な表面実装(SMT)の位置合わせが可能になります。
主に円形または正円に近い形状で、銅箔が露出した状態で設計されることが一般的です。
ねじ穴(Screw Hole / Mounting Hole)
基板や筐体に部品や板を固定するためのねじを通すための穴です。
基板上では、スペーサーや筐体への固定、アース(GND)接続を兼ねる場合もあります。
ねじ穴周囲には、強度確保や導通目的でメタルリング(ランド)や補強パッドを設けることが多く、適切な設計により基板割れや反りの防止、固定強度の向上につながります。
基板取付穴(Mounting Hole)
プリント基板を筐体やスペーサー、シャーシに固定するために設けられた取付専用の穴です。
ねじ、リベット、スペーサー、ピンなどを通し、基板の保持、振動対策、位置決めに使用されます。
基板取付穴には、用途に応じて以下の種類があります。
- 非導通タイプ(ノンメッキホール):絶縁目的で使用される固定用の穴
- 導通タイプ(メタルリング付き):GND接続やシールド用途として使用するタイプ
- 補強パッド付き:基板の強度向上や割れ防止のために、穴周囲に補強パッドを設けたタイプ
適切に設計された基板取付穴は、固定強度の向上、基板破損防止、ノイズ対策(アース接続)にも効果があります。
ミシン目(Perforation / タブ切り)
基板を分割しやすくするために、小さな孔(連続孔)とスリットを設けた加工構造です。
Vカットと同様に分割性向上を目的としたもので、手割りできる基板設計として採用されます。
ベーキング(Baking / 基板ベーキング処理)
基板内部に含まれる湿気(吸湿)を除去するために、一定温度で加熱処理を行う工程です。
湿気を除去することで、はんだ付け時のボイド・クラック・ポップコーン現象などの不良防止に効果があります。
ワークサイズ(Work Size)
製造ラインに投入できる基板(ワーク)の最大/最適サイズを示す設計パラメータです。
設備仕様に適したワークサイズ設計は、生産効率と歩留まりの向上に影響し、実装コストにも関わります。
7
銅箔(Copper Foil / 銅箔材)
プリント基板の導体パターンを形成するために使用される銅製の金属箔です。
用途に応じて、一般的な電解銅箔(Electrolytic Copper Foil)と、高い柔軟性や耐屈曲性が求められる用途に適した圧延銅箔(Rolled Copper Foil)が選定されます。
打痕(Dent)
外力や接触により、基板表面に生じるへこみ(傷)のことです。
打痕が導体(銅箔)層に達していない場合は、一般的にJIS規格上は許容範囲とされていますが、外観品質や信頼性評価の観点から、製造現場では注意すべき項目です。
補助工具・清掃・除去用品
1
はんだ吸い取り線(Solder Wick)
不要なはんだを取り除くために使う細い銅の編み線で、内部には特殊フラックスが含まれています。
はんだごてで加熱すると、溶けたはんだを銅線が毛細管現象によって吸い上げるようにして除去できます。
部品の交換や修正作業時のはんだ除去に最適です。
IPA(イソプロピルアルコール)
はんだ付け後のフラックス残渣や油分、汚れを除去する洗浄液です。
速乾性があり、電子部品や基板の洗浄に広く使われています。
ウエス(Wiping Cloth )
機器や基板、作業台の清掃や拭き取りに使用する布です。
IPA(イソプロピルアルコール)を含ませて使用することで、フラックス残渣や油分・汚れを効果的に除去でき、はんだ付け作業や基板実装後のクリーニングに役立ちます。
マスキングテープ(Masking Tape)
はんだやフラックスが不要な部分に付着しないよう保護するためのテープです。
特に耐熱タイプのマスキングテープは、リフロー工程やリワーク時にも剥がれにくく、部品保護や仕上がり品質の向上に効果的です。
ニッパー(Nipper)
電子部品のリード線や端子を切断するための工具です。
刃先が鋭く、電子基板に使用される小型部品のリードカットに適しており、精密作業や仕上げ品質の向上に欠かせない工具です。
ピンセット(Tweezers)
小型部品の配置や保持に使う基本工具です。
先端の形状(細・斜め・フラットなど)によって用途が異なり、特にSMD(表面実装部品)のチップなどをつかむ精密作業には欠かせません。
ラジオペンチ(ラジペン/Needle Nose Pliers)
細長い先端を持つペンチで、狭い場所での部品のつかみや曲げに最適です。
リード線の整形や配線作業にも広く使われます。
吸着ピンセット(Vacuum Tweezers)
先端で真空吸着して部品を持ち上げるタイプのピンセットです。
BGAなどICを基板上に配置するのに適しています。
フォーミングツール(Forming Tool)
リード部品(抵抗、コンデンサ、LEDなど)の端子形状を曲げたり整形したりして、リードピッチを基板の穴間隔に合わせるための工具です。
DIP(スルーホール)実装前の下準備として使用され、部品の取り付け精度向上や、はんだ付け時の安定した固定に役立ちます。
温度管理機器
1
こて先温度計(Tip Thermometer)
はんだごての先端温度の精度を測定・監視する機器です。設定温度と実測温度の差を確認し、はんだ付け品質を安定させます。定期的な温度チェックで過熱や温度低下による不具合を防止できます。
リフローチェッカー(Reflow Checker)
リフロー炉内の温度分布やプロファイルを測定・記録する機器です。
基板に取り付けた熱電対で実際の温度変化を記録し、設定条件と実測データを比較することで、最適なリフロー条件の確認・管理を行います。
温度の上がり方やピーク温度を分析し、不良発生の防止や品質の安定化に役立ちます。
ディップテスター(Dip Tester)
はんだ槽(ディップ槽)の温度を測定・監視するための装置です。
温度センサーを槽内に入れて、溶融はんだの温度を正確に測定し、適正温度を維持することで、はんだの酸化・不濡れ・ブリッジなどの不具合を防止します。
フローはんだやディップ工程の品質管理に欠かせない測定器です。
静電気対策機器・用品
1
リストストラップ(Wrist Strap)
はんだ付け作業時に手首に装着して静電気を逃がすためのバンドです。
導電性のあるストラップを接地(アース)に接続することで、体にたまった静電気を安全に放電し、電子部品や基板の静電気破壊(ESD)を防ぎます。
静電靴(ESD Shoes)
はんだ付けや電子部品の組立作業時に静電気を逃がすために着用する靴です。
導電性素材で作られており、接地(アース)された床面を通じて体内の静電気を安全に放電します。
イオナイザー静電靴(Ionizer)
作業空間に漂う静電気を中和・除去するための装置です。
マイナスとプラスのイオンを発生させて空気中の電荷を中和し、静電気による電子部品の吸着・放電・破損を防ぎます。
はんだ付けや組立工程など、静電気が発生しやすい環境で使用されます。
制電マット(ESD Mat)
作業台上の静電気を拡散・除去する導電性マットです。
電子部品を扱う机や作業台に敷いて使用し、接地(アース)を取ることで静電気を安全に逃がします。
リストストラップや静電靴と併用することで、より高い静電気対策効果が得られます。
表面実装工程(SMT)
1
はんだ印刷機(Solder Printing Machine)
ペースト状のはんだを基板上に適量を正確に印刷する装置です。
メタルマスクを使用して、ランド部分に均一な厚みではんだペーストを転写します。
印刷精度は、リフロー後のはんだ付け品質に大きく影響するため、かすれや位置ずれ、厚みムラの管理が重要です。
安定した印刷精度を維持することで、はんだブリッジや未接合といった不良を未然に防止します。
ディスペンサー(Dispenser)
はんだペーストや表面実装部品(SMD)固定用の接着剤を基板上に高精度で吐出する装置です。
はんだ量を部分的に補ったり、部品の脱落防止や位置安定化を目的として使用されます。
主に、マウンターによる自動実装工程の前後で使用されます。
マウンター(表面実装機 / Mounter)
表面実装部品(SMD)をプリント基板上に自動で高速・高精度に搭載する装置です。
リフロー炉と組み合わせて使用することで、表面実装(SMT)ラインを構成します。
高い位置精度と生産性を両立し、多品種少量から量産まで幅広い実装に対応します。
かつては「チップマウンター」と呼ばれていましたが、現在のマウンターは進化を遂げ、0402チップ(古賀電子では03015から対応可)などの微小部品からBGA(Ball Grid Array)・QFN(Quad Flat Non-leaded package)・LGA(Land Grid Array)・コネクタなどの大型部品まで1台で搭載可能となったため、総称として「マウンター」と呼ばれるようになりました。
■ マウンターの種類
● モジュラーマウンター(Modular Mounter)
現在主流の方式で、高速性と汎用性を両立しています。
ユニット構造で構成され、実装内容に応じてモジュールを組み替えることが可能です。
多品種・少量生産にも柔軟に対応でき、当社でもこの方式を採用しています。
● ロータリーマウンター(Rotary Mounter)
かつて主流だった方式で、極めて高い搭載速度が特徴です。
回転式のヘッドを用いて、一定種類の部品を大量に処理する量産向けラインに適しています。
リフロー炉(Reflow Oven)
表面実装部品(SMD)をはんだペーストで一括して加熱・接合する装置です。
温度プロファイルは、
プリヒート(予熱) → ソーク(均熱) → ピーク(最高温度) → クーリング(冷却) の4段階で構成されます。
この温度プロファイルを適切に制御することで、はんだ付けの品質と接合強度を安定化させることができます。
挿入実装技術(IMT:Insertion Mounting Technology)
1
部品自動挿入機(Axial/Radial Inserter)
リード部品(抵抗、コンデンサなど)を自動で基板に挿入する装置です。
リード形状(アキシャル/ラジアル)に応じて装置が分かれ、大量生産ラインでDIP部品の高速実装を実現します。
プリヒーター(Preheater)
基板全体を事前に加熱して温度を均一化し、はんだ付け時の熱衝撃を緩和する装置です。
特に多層基板や大型部品の実装時に効果的で、はんだの濡れ性を向上させ、部品への熱ストレスを軽減します。
また、はんだの濡れ性を高めることで接合品質を安定化させる効果があり、フローはんだ付けやディップ実装工程では、フラックスを活性化させるための最適な温度設定を実現します。
はんだ槽(ディップ槽)
棒はんだを溶融して液状化した槽に基板を浸すことで、裏面の部品を一括ではんだ付けする装置です。
ディップ実装やフローはんだ付け工程で使用され、生産効率の高い量産対応が可能です。
自動搬送や温度制御により、安定したはんだ品質を確保します。
治工具類
1
メタルマスク(Metal Mask)
はんだ印刷機で基板上に正確な量のはんだペーストを転写するためのステンレス製マスクです。
ランド(電極)部分のみに開口部を設け、スクリーン印刷のようにスキージでペーストを押し出して印刷します。
スキージには、ウレタン製・メタル製・プラスチック製の3種類があり、印刷条件やペーストの粘度、マスクの開口形状に応じて最適なものを選定します。
メタルマスクの開口形状や厚みは、はんだ量・濡れ性・リフロー後の接合品質に直結するため、製品仕様や部品形状に合わせた精密な設計・製作が不可欠です。
また、はんだ印刷はSMT(表面実装技術)の中でも品質を大きく左右する工程であり、廉価なものも流通していますが、国内製の高品質メタルマスクの使用を推奨します。
さらに、はんだ印刷機の構造上、基板の表面・裏面それぞれに専用のメタルマスクが必要です。
特殊装置(はんだ付け)
1
ホットエアーガン(Hot Air Gun)
局所的に熱風を当てて加熱するハンドツールです。
主に表面実装部品(SMD)の部品交換(リワーク)や補修作業に使用され、狭い範囲を効率的に加熱できます。
はんだを溶かして部品を取り外したり、再装着したりする際に使用され、簡易的に作業が行えるのが特長です。
リワーク装置(Rework Station)
表面実装部品(SMD)の取り外し・搭載・交換に使用する加熱装置です。
温度と風量を制御でき、はんだを溶かして部品を安全に取り外したり再装着したりできます。
主にBGA(Ball Grid Array)・QFN(Quad Flat Non-leaded package)・LGA(Land Grid Array)など電極が部品の底面にあり、はんだごてでは作業できない部品の場合に使用します。
検査装置
1
はんだ検査機(SPI:Solder Paste Inspection)
はんだ印刷後のはんだペーストの状態を測定・検査する装置です。
三次元のものは、印刷位置、体積、高さなどを自動で測定し、印刷不良(かすれ・にじみ・ブリッジ)を早期に検出します。
はんだ付け品質の安定化に欠かせない検査装置です。
基板外観検査機(AOI:Automatic Optical Inspection)
実装基板上のはんだ状態や部品実装の良否を自動で検査する装置です。
複数の高解像度カメラと照明を用いて撮像し、外観データを解析することで、はんだブリッジ・浮き・ずれ・欠品・極性間違いなどを高精度に検出します。
X線検査装置(X-ray Inspection System)
BGA(Ball Grid Array)・QFN(Quad Flat Non-leaded package)・LGA(Land Grid Array)など、底面電極を持つ部品のはんだ接合状態を観察する装置です。
これらの部品は電極が外から見えない構造のため、X線を透過させて内部のはんだ接合部を非破壊で検査します。
X線画像により、以下のような不良を検出できます。
- ボイド(はんだ内部の気泡)
- 未接合・オープン
- はんだブリッジ(ショート)
- はんだ量の過不足
これにより、リフロー条件の最適化や実装品質の安定化に大きく寄与します。
CT検査装置(CT Inspection System)
X線装置と同様に非破壊で内部観察を行う装置ですが、複数方向から撮影したX線画像を3D再構築(断層撮影)することで、より詳細な内部構造を確認できます。
特に、BGA(Ball Grid Array)・QFN(Quad Flat Non-leaded package)・LGA(Land Grid Array)などの電極と基板の接合界面は、X線装置では見えづらい箇所が存在します。
CT装置を用いることで、「接合形状の立体的把握」「ボイド位置の正確な特定」「微細な未接合部の可視化」が可能となり、より高度な品質解析と不良原因の特定に役立ちます。
観察・測定器
1
ヘッドルーペ(Head Loupe)
頭部に装着して両手を自由に使いながら作業できる拡大鏡です。
部品やはんだ接合部を拡大しながら正確に観察・作業できます。
顕微鏡(Microscope)
部品やはんだ接合部を拡大して詳細に観察するための光学観察装置です。
高倍率で拡大できるため、肉眼では確認できない微細なクラック・ボイド・異物・濡れ不良などを正確に検出できます。
用途に応じて以下の種類を使い分けています:
- 実体顕微鏡(Stereo Microscope):
立体視が可能で、はんだの盛り上がりや部品の角度を三次元的に確認可能。
手はんだ・リワーク・検査作業に最適です。
- マイクロスコープ(Digital Microscope):
高倍率かつデジタル表示で、微細なパターンや接合状態を詳細に観察できます。
撮影・記録機能により、品質分析や教育資料の作成にも活用しています。
顕微鏡による観察は、はんだ品質の安定化・不良解析・品質改善活動に欠かせないプロセスの一つです。
マルチメーター(Multimeter / Tester)
電圧、電流、抵抗などの複数の電気量を測定できる多機能な電気計測器です。
LCRメーター
インダクタンス(L:コイルの値)、キャパシタンス(C:コンデンサの値)、抵抗(R)の電気特性を測定する専用計測器です。
オシロスコープ(Oscilloscope)
電気信号の波形を画面に可視化して観測する装置です。
電子部品関連
パッケージ・実装形式
1
ASIC (ASIC:Application Specification Integrated Circuit)
特定用途に最適化された集積回路。
汎用ICとは異なり、機能・構造が事前に固定されており、量産性・性能・消費電力の面で優れる。
家電・通信・産業機器など、用途特化型の設計に使用されます。
BGA (Ball Grid Array)
ICパッケージの底面に格子状に配置されたはんだボールを接点とする実装形式。
高密度・高集積化が可能で、QFPよりも小型化・多端子化に適します。
ただし、実装後の目視検査が困難なため、X線検査などの非破壊検査が必要です。
COB (Chip On Board)
ベアチップ(裸の半導体)を基板上に直接搭載し、ワイヤボンディングで接続する実装方式。
パッケージを省略することで小型化・コスト削減が可能ですが、封止樹脂による保護や環境耐性確保が求められます。
CSP (Chip Size Package)
チップサイズに近い寸法で構成された小型パッケージ。BGAと同様の構造を持つが、パッケージ外形がチップ寸法に近く、高密度実装・省スペース化に適する。モバイル機器などに多用されています。
DIP (Dual inline Package)
両側面からリード端子が出ている直列配置型パッケージ。
スルーホール実装に対応し、手はんだ・試作・教育用途などに適しています。
古典的ですが、信頼性と扱いやすさから現在も一部で使用されています。
IC(Integrated Circuit(集積回路))
複数の電子回路素子(トランジスタ・抵抗・コンデンサなど)を1つのチップ上に集積した構造体。
論理処理・制御・演算・記憶など、電子機器の中枢機能を担います。
パッケージ形式により、実装方法や放熱特性が異なります。
LGA (Land Grid Array)
BGAに類似したパッケージですが、はんだボールの代わりに平面接点(ランド)を持つ構造です。
接触面積の制御や熱設計が重要で、高密度・薄型実装に適しています。
MCM (Multi Chip Module)
複数のICや小型部品を1つのモジュール内に集積した構造体。
機能統合・省スペース化・高性能化を目的とし、通信・医療・産業機器などで使用されます。
内部にはCOBやBGAなど複合実装形式が用いられます。
SMD (Surface Mount Device)
表面実装型の電子部品全般を指す総称。
リード線を持たず、基板表面に直接はんだ付けされる構造で、高密度・小型化に最適。
自動実装ライン(SMT)における主流形式です。
SOP (Small Out-line Package)
DIPに似た形状ながら、表面実装(SMD)対応の小型パッケージ。
リード端子が側面から出ており、省スペースかつ量産性に優れます。
アナログIC・ロジックICなどで幅広く使用されています。
チップ抵抗(Chip Resistor)
表面実装型(SMD)の抵抗器であり、プリント基板上に直接はんだ付けされる電子部品です。
電流の制限、電圧の分割、信号のプルアップ/プルダウンなど、回路の基本動作を支える構成要素です。
主な用途
- 電流制限(LED保護など)
- 電圧分割(センサ入力調整など)
- 信号ラインのプルアップ/プルダウン
- フィルタ回路の構成要素
- 電源ラインのノイズ吸収(他部品との組み合わせ)
「チップ」は実装形態の呼称であり、構造形式を指すものではありません。
チップコンデンサ(Chip Capacitor)
SMD形状を持つコンデンサの総称で、積層セラミックコンデンサ(MLCC)が代表的。
構造や材料に応じて、電解型・フィルム型・タンタル型などもあります。
「チップ」は実装形態の呼称であり、構造形式を指すものではありません。
CR(Capacitor & Resistor)
コンデンサ(C)と抵抗(R)の総称。
アキシャル部品(Axial Component)
部品の両端からリード線(足)が軸方向に出ているタイプの部品です。
リードが左右にまっすぐ伸びており、部品本体を寝かせて基板に実装するのが一般的です。
代表例:
- カーボン抵抗器(抵抗)
- ダイオード
- 一部の電解コンデンサ
ラジアル部品(Radial Component)
部品の片側から2本以上のリードが放射状(ラジアル方向)に出ているタイプです。
部品本体を基板に対して垂直に立てて実装します。
代表例:
- 電解コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- LED
- トランジスタ
- 各種コイル
コネクタ
電子機器や電子部品に使用される電気および信号をつなぐ接続部品です。例えば、機器と機器をつないだり、機器内の基板とモジュールをつないで電気を通します。
これより下は掲載するか要検討
タイミング・周波数制御部品
1
タイミングデバイス(Timing Device)
電子回路やシステムにおいて、正確な時間・周波数・同期信号を生成・制御するための部品や回路の総称です。
主にクロック信号の生成や、複数の回路・通信のタイミングを一致させるために使用されます。
代表的なものには、水晶振動子、セラミック振動子、RTC(リアルタイムクロック)、PLL(位相同期回路)、タイマーICなどがあります。
水晶振動子(Crystal Oscillator)
安定した周波数の発振源であり、電子機器のクロック生成に使用されます。
高精度・低温度特性に優れ、通信機器・制御装置・計測機器などで広く利用されています。
セラミック振動子(Ceramic Resonator)
小型で安価な周波数源。
水晶振動子に比べて精度はやや劣りますが、マイコンなどの内蔵クロックや一般機器に多用されます。
構造が簡易でコストパフォーマンスに優れています。
RTC(リアルタイムクロック / Real-Time Clock)
電源がOFFの状態でも時刻情報を保持できる時計回路です。
バックアップ電池を用いて動作し、時刻管理やスリープ復帰制御などに使用されます。
時計機能付きマイコンや通信装置などで採用されています。
PLL(位相同期回路 / Phase-Locked Loop)
周波数の乗算・分周・同期制御。
タイマーIC(Timer IC)
基準信号と比較して周波数や位相を自動制御する電子回路です。
周波数の乗算・分周・同期制御に利用され、通信・映像・音響機器で信号の安定化に貢献します。
SAWデバイス(Surface Acoustic Wave Device)
表面弾性波(Surface Acoustic Wave)を利用して、信号のフィルタリングや周波数制御を行う電子部品です。主に高周波回路や通信機器に使用されます。
電気信号を圧電体表面の音響波に変換し、周波数選択性や共振特性を利用して信号処理を行う構造的部品である。 フィルタやレゾネータとしての役割を持ち、高周波通信の安定性と選択性を保証する技術的基盤となっている。
SAWフィルタ(SAW Filter)
特定の周波数帯域を通過または遮断するためのフィルタ素子です。
通信機器のノイズ除去・周波数選択性向上に利用されます。
SAWレゾネータ(SAW Resonator)
表面弾性波の共振現象を利用し、安定した共振周波数を生成する素子です。
高周波通信や発振回路での基準周波数生成・安定化に使用されます。
コンデンサ群(蓄電・フィルタ)
1
コンデンサ(Condenser)= キャパシタ(Capacitor)
電気エネルギーを静電的に蓄える電子部品であり、2つの導体(電極)間に絶縁体(誘電体)を挟んだ構造を持ちます。
■ 主な役割
- 電荷の蓄積と放出:電圧変化に応じて電流を流したり止めたりします。
- フィルタ機能:ノイズ除去・電源平滑化・タイミング制御などに使用。
- 周波数特性:種類によって高周波・低周波への適応性が異なります。
キャパシタは、電子回路における電気的な緩衝・調整・蓄積を担う基本部品であり、
電源安定化・信号処理・タイミング制御など、回路の動作安定性に直結する重要素子です。
なお、「コンデンサ」と「キャパシタ」は名称の違いのみで、技術的には完全に同義です。
電解コンデンサ(Electrolytic Capacitor)
大容量・極性ありのコンデンサ。
主に電源回路の平滑・フィルタ・エネルギー蓄積用途に使用されます。
アルミ電解・タンタル電解などがあり、大電流用途や低コスト設計に適しています。
セラミックコンデンサ(Ceramic Capacitor)
主にノイズ除去・バイパス・デカップリング用途で使用されます。
SMD(表面実装)型の積層セラミックコンデンサ(MLCC)が主流です。
フィルムコンデンサ(Film Capacitor)
プラスチックフィルムを誘電体として使用したコンデンサ。
温度特性・安定性が高く、音響機器・高電圧・インバータ回路などに使用されます。
低損失・長寿命で、高信頼性が求められる用途に適しています。
タンタルコンデンサ(Tantalum Capacitor)
タンタル金属を使用した小型・高容量のコンデンサ。
極性があり、主に携帯機器・制御装置・省スペース基板に採用されます。
安定した容量特性を持ちますが、過電圧に弱いため設計時には保護が必要です。
半導体・パワー半導体
1
半導体(Semiconductor)
電気を通す導体(金属など)と、電気を通さない絶縁体(ガラスなど)の中間的な性質を持つ物質です。
温度や不純物(ドーピング)の影響によって導電性が変化する特徴を持ち、
電子機器の制御・スイッチング・演算に欠かせない材料です。
主な機能として:
- スイッチング機能:トランジスタとして電流をON/OFF制御
- 整流機能:ダイオードとして電流の流れを一方向に制御
- 演算機能:ICやCPUとして論理処理や信号演算を実行
このように半導体は、電気信号の流れを制御する基盤技術として現代の電子機器を支えています。
パワー半導体(Power Semiconductor)
大電力(高電圧・大電流)を制御・変換するために設計された半導体素子の総称です。
主に電源回路、モーター制御、電力変換(インバータ・コンバータ)などに使用されます。
信号を制御する一般半導体に対し、電力そのものを扱うため“パワー”の名が付けられています。
代表的な素子には以下のものがあります。
パワーMOSFET(Power MOSFET)
高速スイッチングが可能で、低電圧・中電流の制御用途に使用されます。
スイッチング電源・DCモータ制御・車載電子機器などに適しています。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)
高電圧・高電流制御に適したパワーデバイスです。
MOSFETの高速性とバイポーラトランジスタの高耐圧特性を併せ持ちます。
主な用途は、産業用インバータ・エアコン・太陽光発電システム・ハイブリッド車(HV/EV)などです。
ダイオード(Power Diode)
電流を一方向のみに流す整流素子です。
主に電源回路(AC→DC変換)・モータ制御・充電回路などに使用され、逆流を防止します。
サイリスタ(Thyristor)
大電力のスイッチング制御が可能な半導体素子です。
主に交流制御・電力変換装置・整流器などで使用されます。
高耐圧・高電流特性を持ち、電力制御用途に適します。
FRD(ファストリカバリダイオード / Fast Recovery Diode)
PN接合によるダイオードで、構造や機能は一般整流ダイオードと同じです。一般整流ダイオードは商用周波数の整流に適していることに対し、ファストリカバリダイオードは、逆回復時間(trr)が速く、高周波の整流に適している
SBD(ショットキーバリアダイオード / Schottky Barrier Diode)
PN接合ではなく、金属電極とn型半導体の接触による電位障壁(ショットキーバリア)を利用したダイオードです。
順方向電圧(VF)が低く、逆回復時間(trr)が短いため、高速スイッチング回路に最適です。
電源回路や高周波回路など、効率重視の設計に多用されます。
一般整流ダイオード(Rectifier Diode)
外部制御なしで電圧の極性に応じて自律的に整流動作するダイオードです。
交流(AC)を直流(DC)に変換するための基本素子であり、電源回路・モータ制御・充電器などに幅広く使用されます。
対になる用途として、高速動作用のスイッチングダイオードがあります。
スイッチングダイオード(Switching Diode)
高速でON/OFF(導通/遮断)を切り替えることができるダイオードです。
信号処理・ロジック回路・通信機器などに使用され、数ナノ秒〜数マイクロ秒の高速応答を実現します。
特徴:
- 高速応答(高速スイッチング)
- 低容量・低電流設計(信号レベル動作に最適)
- 論理回路・マイコン・通信機器などでの信号制御用途
主な用途:
クロック信号整形・デジタル信号ルーティング・高速スイッチング・逆電圧保護回路など。
抵抗・センサ・制御部品
1
可変抵抗(Potentiometer)
抵抗値を手動または機械的に変化させることができる電子部品です。
つまみやスライダーの操作によって、抵抗値を連続的に変化させる構造を持ちます。
主に電流・電圧の調整や信号レベル制御に用いられます。
主な用途
- 音量調整(オーディオ機器のボリューム)
- 明るさ制御(照明調整)
- センサ感度の調整
- 電圧分割による基準電圧生成
- ユーザー操作によるアナログ入力(マイコン接続)
サーミスタ(Thermistor)
温度によって抵抗値が変化する電子部品であり、温度検出や温度補償に使用されます。
「Thermal(熱)」+「Resistor(抵抗)」の合成語で、温度変化を電気信号に変換します。
主な用途
- 温度検出(家電・バッテリー・モーターなど)
- 過熱保護(温度上昇時の電流制限)
- 温度補償(回路動作の安定化)
- 起動時の突入電流制限(NTC型)
LDR(光依存抵抗 / Light Dependent Resistor)
光の強さによって抵抗値が変化する電子部品です。
明るさが強いほど抵抗が小さくなる特性を持ち、光を電気信号に変換します。
主な用途
- 明るさ検出(照度センサ)
- 自動点灯制御(街灯・バックライト)
- 光追従制御(ロボット・玩具など)
- 簡易フォトセンサ(マイコン入力)
温度センサ(Temperature Sensor:Thermocouple / RTD)
温度を電気信号に変換するセンサ部品です。
熱電対(Thermocouple)は異種金属接点による電圧発生を利用し、
RTD(抵抗温度検出器)は温度変化による抵抗値変化を利用します。
主な用途
- 産業機器・家電・車載機器の温度監視
- ヒーター・冷却装置の温度制御
- バッテリー・モーターの過熱保護
- 環境モニタリングや温度計測
光センサ(Light Sensor:Photodiode / LDR)
光を電気信号に変換する電子部品です。
フォトダイオードは高速応答で光を電流に変換し、LDRは光量に応じて抵抗値を変化させます。
主な用途
- 照度検出・自動点灯制御(街灯・バックライト)
- 光通信・フォトインタラプタ
- マイコンによる明るさ判定
- 玩具・ロボットの光追従制御
加速度センサ(Accelerometer)
物体の加速度(動き・振動)を検出し、電気信号として出力するセンサです。
静電容量型・圧電型などの構造があり、三軸検出が可能なタイプも存在します。
主な用途
- スマートフォン・ゲーム機の動作検出
- 車載機器の衝突検知・エアバッグ制御
- 産業機器の振動監視
- ウェアラブル機器の歩数・姿勢検出
ジャイロセンサ(Gyroscope)
物体の回転角速度を検出する電子部品です。
MEMS技術による小型化が進み、三軸回転の検出も可能です。
加速度センサと組み合わせて姿勢制御や動作解析に使用されます。
主な用途
- ドローン・ロボットの姿勢制御
- スマートフォンの画面回転検出
- 車載ナビの方向検出
- ゲーム機・VR機器の動作追従
- 産業機器の回転監視
インダクタ・磁性部品・電源制御
1
インダクタ(Inductor)
電流の変化に抵抗する性質(自己誘導)を利用する電子部品です。
電流が流れると磁場を発生させ、その磁場によって電気の流れを制御します。
主にフィルタ回路・電源回路・共振回路などに使用され、エネルギーの蓄積やノイズ除去に欠かせません。
主な用途
- 電源回路のノイズ除去(LCフィルタ)
- スイッチング電源でのエネルギー蓄積(DC-DCコンバータ)
- 高周波回路の共振・整合(RFインダクタ)
- モーター駆動回路での突入電流緩和
- 信号ラインのチョークコイルとして高周波ノイズを遮断
チョークコイル(Choke Coil)
インダクタの一種で、不要な高周波成分(ノイズ)を遮断し、直流や低周波信号のみを通す部品です。
「チョーク(choke)」=「絞る」という意味で、電源ラインや信号ラインのノイズ対策に使用されます。
主な用途
- 電源ラインの高周波ノイズ除去(DCラインフィルタ)
- 信号ラインの高周波成分フィルタリング
- 共通モードノイズの抑制(共通モードチョーク)
- スイッチング電源のEMI対策
- オーディオ回路のハムノイズ除去
トランス(Transformer)
電磁誘導の原理を利用して電圧や電流を変換し、回路間の電気的絶縁を行う部品です。
電源回路や信号伝送回路で使用され、電気エネルギーを安全かつ効率的に伝達します。
主な用途
- 電圧変換(昇圧・降圧)
- 電流変換(検出回路・電流トランス)
- 回路間の絶縁(安全対策・ノイズ防止)
- インピーダンス整合(音響・通信回路)
- 高周波信号伝送(RFトランス)
レギュレータ(Voltage Regulator)
入力電圧の変動に関わらず、一定の出力電圧を維持する電子部品または回路です。
電子機器やマイコンなど、安定した動作電源が必要な回路に不可欠な存在です。
主にリニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2種類があります。
● リニアレギュレータ(Linear Regulator)
トランジスタを用いて電圧を安定化させる方式で、ノイズが少なく応答性に優れるのが特徴です。
ただし、余分な電圧を熱として消費するため、効率は低めです。
主な用途:
- マイコン・センサなど低ノイズを求める電源
- アナログ回路やオーディオ回路の電圧安定化
- 精密基準電圧回路
● スイッチングレギュレータ(Switching Regulator)
スイッチング素子(MOSFETなど)を高速でオン・オフ制御し、高効率で電圧を変換・安定化させる方式です。
DC-DCコンバータの主要構成要素であり、昇圧・降圧・反転など柔軟な電源設計が可能です。
主な用途:
- スイッチング電源・DC-DCコンバータの制御部
- バッテリー駆動機器の高効率電源制御
- 産業機器・車載電源・通信機器など
● 主な機能
- 電圧の安定化(リップル除去・瞬時変動補正)
- 過電流・過熱・短絡保護
- 電源ラインのノイズ抑制
- 電圧変換(昇圧/降圧)
DC-DCコンバータ(DC-DC Converter)
直流電圧を別の直流電圧に変換する電子回路またはモジュールです。
電圧の昇圧・降圧・安定化を行い、マイコンやセンサなどに必要な安定した電源を供給します。
主な用途
- マイコン・センサへの安定電源供給
- バッテリー駆動機器での電圧調整(昇圧・降圧)
- USB電源からの多電圧生成(5V→3.3Vなど)
- 太陽光発電・車載・産業機器の電力変換
スイッチング電源(Switching Power Supply / SMPS)
スイッチング素子(MOSFETなど)を高速でオン・オフ制御し、電力を高効率に変換する電源回路またはモジュールです。
電圧変換・絶縁・安定化を高効率で実現し、DC-DCコンバータの上位概念にあたります。
主な用途
- AC-DC変換(AC100V → DC12Vなど)
- DC-DC変換(DC24V → DC5Vなど)
- LED照明・モータ制御・通信機器・産業機器の電源供給
- バッテリー充電器・PC電源・電源アダプタ
バッテリ(Battery)※実装型
化学反応により電気エネルギーを蓄え、必要時に放出する電源部品です。
ここでは、プリント基板上に直接はんだ付けして使用する「実装型バッテリ」を指します。
主な用途
- RTC(リアルタイムクロック)のバックアップ電源
- 一時的な電源保持(停電・電源断対策)
- 小型機器の動作用電源(ウェアラブル・IoTセンサなど)
- マイコン設定保持(EEPROM代替・記憶保持)
保護部品・EMC対策
1
ヒューズ(Fuse)
過電流が流れた際に内部導体が溶断して回路を遮断し、電子機器や部品を保護する構造的電子部品です。
一定以上の電流が流れると意図的に破壊される「使い捨て型保護素子」であり、過電流による発熱・発火を防止します。
主な用途
- 電源回路の過電流保護
- バッテリー・モーター・高電力負荷の安全遮断
- 家電・産業機器・車載機器の故障防止
- マイコン周辺や制御基板の低電流保護
バリスタ(Varistor)
過電圧を吸収・分散して回路を保護する電子部品です。
“Voltage”+“Resistor”の合成語で、電圧が一定値を超えると急激に抵抗値が下がり、サージエネルギーを吸収します。
主な用途
- 電源ラインのサージ保護(雷・静電気・突入電圧)
- 通信回路・制御回路の過電圧対策
- 家電・産業機器・車載機器のEMC対策
- AC電源ラインの過電圧吸収
ESD保護ダイオード(ESD Protection Diode)
静電気放電(ESD)による高電圧パルスから電子回路を保護するダイオード型素子です。
瞬時に過電圧を吸収・クランプし、ICや通信ラインの破損を防ぎます。
特に微小信号・高速通信回路の保護に欠かせません。
主な用途
- USB、HDMI、LANなど高速通信ポートのESD対策
- マイコン・センサ・液晶モジュール入力端子の保護
- タッチパネル・スイッチ・外部端子の静電気防止
- 車載・産業機器の外部インターフェース保護
サージアブソーバ(Surge Absorber)
突発的な過電圧(サージ)を吸収・分散し、電子回路を保護する部品です。
雷・スイッチング・静電気などによる高電圧パルスを抑制し、電子機器の誤動作や破損を防ぎます。
主な用途
- 電源ラインの雷サージ対策
- モーター・リレー駆動時の誘導サージ吸収
- 通信・制御回路の過電圧保護
- 家電・産業機器のEMC(電磁両立性)対策
フェライトビーズ(Ferrite Bead)
高周波ノイズを吸収・減衰させる磁性体部品です。
通常の動作信号はそのまま通過させつつ、不要な高周波ノイズのみを遮断・損失させます。
小型で表面実装型(SMDタイプ)が主流です。
主な用途
- 電源ラインの高周波ノイズ除去
- マイコン・センサ周辺のEMI対策
- USB・HDMI・LANなど高速信号ラインのノイズ抑制
- スイッチング電源・通信機器のEMC対策
表示・出力・音響部品
1
LED(Light Emitting Diode)
電流を流すことで発光する半導体素子です。
低消費電力・長寿命・高速応答が特徴で、表示・照明・通信など幅広い用途に利用されます。
主な用途
- インジケータ表示(電源・状態表示)
- 照明(バックライト・ランプ・ディスプレイ)
- 光通信(リモコン・赤外線送受信)
- 装飾・演出(看板・イルミネーション)
7セグメントLED(7-Segment LED)
数字や記号を表示するために構成された7個のLED素子の集合体です。
各セグメントを個別制御することで「0〜9」や一部文字を表示します。
主な用途
- デジタル表示(時計・温度計・電圧計など)
- 家電・計測機器の数値表示
- マイコン制御による簡易UI表示
- 産業機器の状態表示
LCDモジュール(Liquid Crystal Display Module)
液晶を用いた表示部品で、電圧により液晶分子の配向を制御し、光の透過/遮断で文字や画像を表示します。
低消費電力で静止画表示に適しています。
主な用途
- 情報表示(家電・リモコン・計測器など)
- マイコン制御によるUI表示
- 産業機器・医療機器の画面表示
- バッテリー駆動機器の省電力表示
OLEDモジュール(Organic Light Emitting Diode Module)
有機ELを用いた自発光型の表示デバイスです。
高コントラスト・広視野角・薄型構造が特徴で、バックライトを必要としません。
主な用途
- スマートフォン・ウェアラブル機器の高精細表示
- 家電・IoT機器のステータス表示
- 産業機器の小型表示装置
- 暗所での高視認性ディスプレイ
マイクロフォン(Microphone)
音波(空気振動)を電気信号に変換する電子部品です。
ダイナミック型、コンデンサ型、MEMS型などがあり、音声入力や音響測定に利用されます。
主な用途
- 音声認識・通話機能(スマートフォン・PC)
- 録音・集音(カメラ・レコーダー)
- 騒音検出・音響センサ用途
- IoT機器の音声トリガー入力
スピーカー(Speaker)
電気信号を音波(空気振動)に変換する電子部品です。
コイルと振動板の構造により、音声・音楽・警告音を出力します。
主な用途
- 音声出力(スマートフォン・PC・家電)
- アラーム・警告音(セキュリティ・医療機器)
- 音響再生(オーディオ機器・テレビ)
- 音声ガイド・案内装置
タッチパネル(Touch Panel)
指やスタイラスによる接触を検出し、座標情報を電気信号に変換する入力デバイスです。
抵抗膜型・静電容量型などがあり、表示部と一体化される構造が一般的です。
主な用途
- スマートフォン・タブレットの操作入力
- 産業機器・医療機器のタッチUI
- ATM・券売機などのユーザー操作パネル
- 家電・制御装置のタッチ式入力